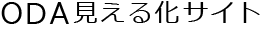ワーキンググループ第1回全体会議を開催しました。
2024 年4月2日(火)、日本モンゴル病院で、医師の卒後研修に関わる3つのワーキンググループ(WG)の活動が開始されるのに先駆けて、メンバー全員が一堂に会する全体会議を行いました。
まず、議長のBolortuya先生(日モ病院副院長)より、本日の会議の目的が、今後行っていく活動の全体像の把握、メンバー紹介、メンバー同士の顔合わせであることが述べられました。
次に、医科大学専門向上局局長のBayasgalan先生から開会の辞があり、続いてWG結成の目的などを以下のように説明されました。
医科大学は、今後の医学教育をこの病院を拠点にして行っていくつもりである。このプロジェクトでは主に卒後研修に関する活動を行っていく。医科大の今年の目標のひとつは、卒後研修を次のレベルに前進(Advance to the next level)させるというものであるので、このプロジェクトと協力し合い、卒後研修の質のレベルを高め、教育病院としての機能をより一層強化していきたい。WGメンバーは、各活動と関連性を持てるような人材を選ばせて頂いた。活動は、この病院の特徴というものを含めながら医科大の政策、方針から外れないで、ハイブリッドという形で両立させ、実施したい。
チーフアドバイザーの嶋田は、日本モンゴル病院でのJICAプロジェクト全体についての説明を行いました。本プロジェクトは、このWGが活動する教育(卒後研修)だけではなく、臨床(診療)、研究、更に財務・運営などの活動も含まれており、実際すでに他のWGも活動している、とこれらの活動との関連性を強調しました。
その後、各WGの活動内容とリーダーを確認し、それぞれの実務担当者(秘書)も指名されました。
WG1:研修の管理、体制 (Bolortuya先生)
WG2:研修の内容、カリキュラム (Bayasgalan先生)
WG3:研修に関わる医療従事者の指導方法・能力の向上 (Bayasgalan先生)
その他、メンバー間の連絡手段とするプラットフォームが選定され、全体会議の頻度(目安として2−3ヶ月に1回行う)が決定されました。
さて、WGメンバー全員に対して本全体会議の前週に、「この病院からどういう医師・看護師を送り出したいですか?」と質問し、予め意見を募っていました。詳細はここでは割愛しますが、寄せられた意見を下に、本全体会議では同じテーマでメンバーみんなで改めて「現実的な」議論をしてもらおうという目算でした。議論は主に医師について行われ、看護師についてはほとんどなかったのは残念ですが、目論見通りメンバーの誰もが何かひと言でも言わんとする熱心なものになりました。
その結果、日モ病院から送り出す医師に対して、「十分な知識、能力、姿勢(態度)を備え、高い倫理性と人間性を持ち、継続的に専門性を磨き続ける意志があり、革新的であり、他業種などとのチームプレイに長け、研究者としての能力も高い・・・など」という極めて高い目標が掲げられました。一見、自分のことは棚に上げ、途方もない要求を若いこれからの医師に求めているようにも見えます。しかし、実は、WGのメンバーのこれからの活動に対するやる気、熱意、意気盛んな様子を表現しているに過ぎません。乞うご期待、です。
なお、今後は連携を保ちながら、各WGがそれぞれ独自課題の下に活動することになります。
文責:チーフアドバイザー 嶋田

会合の様子。
(左)医科大学専門向上局局長Bayasgalan先生の説明
(右)「この病院からどういう医師・看護師を送り出したいか?」議論中